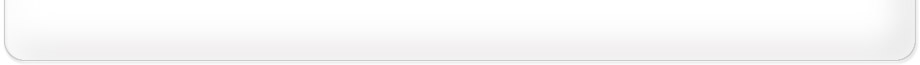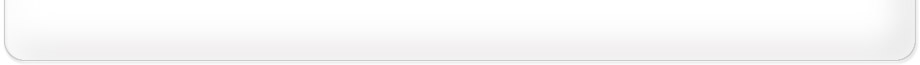|
窓の少ない廊下を一人歩く。
ミハイルはもう部屋に入ったようだ。ドアを開閉する音が、少し前に耳に届いている。
ミハイルの部屋とアロンの自室は、階は同じだが建物が違う。
城の中の居住区は大きくわけて二つ。父親であるヴァレンテ公の住む最奥と、玉座の間を左右に挟む形で建てられた四兄弟のための館がそれにあたる。
領主の妻のための部屋は、使われなくなって久しい。
「……ん?」
部屋に向かう途中、ファウストの部屋を一礼して出てきた執事に出会った。執事は、外見上も実年齢も高齢の紳士で、アロンの記憶にある限りその姿が変化したことはない。
|
 |
|
「兄貴への説教は終わったのかい?」
アロンが声をかけると、執事はアロンの方に向きなおり、一礼する。
執事も当然人間ではないから、近づいてきていたアロンの気配には気付いていたのだろう。
「良い機会ですので、ヴァレンテ家の成り立ちから現在に至るまでの歴史と、その次期当主の責任について、ご説明させていただきました」
|
|
アロンは苦笑をこらえつつ、そうなんだ、と頷いた。
耳にタコができるほど聞かされた話を、一字一句繰り返し、休憩なしで語られたファウストを思うと同情しそうになるが、それでどうにかなるファウストではないだろう。今はげんなりしているだろうが、どうせまたすぐに城を抜け出すにきまっている。
「ファウスト兄貴も懲りないな」
「次はぜひ魔界の成り立ちからご説明させていただきたいと思います」
表情一つ変えず言う執事に、アロンはまたも苦笑する。
そのうち、ファウストは魔界の歴史年表を暗唱できるようになるかもしれない。
「まあでもその機会もしばらくはないよ。明日から向こうだからさ」
「その件ですが、アンリエッタ様からお手紙が届いております。お部屋に届けさせてありますので、どうぞ、ご確認ください」
「アンリエッタから?」
「ご旅行の話がお耳に入られたご様子です」
「あー……」
アロンは息を吐き、頭をかいた。
「その返事、戻ってきてからでもいいだろ」
「できるだけ早急にご返信を、とのことです」
「……長くても一年くらいで戻ってくるのになぁ」
人間界行きは、短くて数週間、長くてもせいぜい一年程だと聞いている。そのくらいの時間は、ヴァンパイアにとっては大したことではない。その気になれば、眠ったままでも過ごせるほどに。
その程度の間は放っておいてほしいものだが、年下の少女を泣かせてもいい気分はしない。
アロンは仕方なく執事に頷く。
「返信は面倒だから、花でも贈っておくよ。庭の白薔薇が見頃だろう? アロンの名で頼む」
「承りました」
「ジョシュアはどうしてる?」
「さきほどアロン様がミハイル様に仰られた通り、未だ持ち物を選んでらっしゃるかと」
「なんだ、聞いてたのか」
「申し訳ございません」
「いや、気にしないでくれ」
この執事はとても耳が良い。必要な時にすぐに現れることができるよう執事として鍛えた能力なのかはわからないが、ヴァンパイアであるアロンから見ても、異様なほどだ。
昔、そのことを不思議がった幼いアロンが父に聞いたところによると、この執事の本体は、ヴァレンテ家居城そのもので、目の前にいる人型の姿は仮の姿だとのことだが、それが冗談なのか真実なのかは未だ不明である。
「じゃ、俺、自分の支度が終わったらジョシュアの様子見に行ってくるよ。
アンリエッタに花、頼むな。」
その場で一礼する執事を背に、アロンは廊下を歩いて行く。
玉座の間を回り込み、館の一方へ。その途中、空中回廊で足を止めた。
回廊には大きく窓が切ってあり、ヴァレンテ家の領地が一望できるようになっている。
そこにあるのは、蒼白い月の光に包まれた、暗灰色の建物の群れ。
常に闇と霧が立ち込め異形の者たちが跋扈する、魔の世界だ。
朝も夜も変わりのないこの景色を、アロンはずっと見続けてきた。
寿命に限りも果てもない、そういう存在があふれているから、この世界の物事は停滞し、動かない。
ここは何万年もの間、無数の建築物にもそこに棲む者にも、変化らしい変化のない閉ざされた牢獄なのだ。
「……ファウスト兄貴じゃないけど、飽きちまうよな」
毎日がとても退屈で、これといった楽しみがなくて、だから魔界では闘争が起きる。
貴族同士で、血族同士で、個人同士で、終わりのない争いは繰り返される。
娯楽らしい娯楽がないのだから、血を好む彼らの社会でそれはある意味仕方のないことだ。
その魔界において、一族内での争いのないヴァレンテ家は非常に珍しい。
四人も後継者候補がいるのだから、いつ殺し合いになってもおかしくはないのだが、アロンにはそのつもりはないし、他の兄弟たちも同じ考えのようだ。
がしかし、四貴族の他の家では、凄惨な出来事が日常的にあるという。
「まったく、もっと建設的なことやればいいのにな」
そう、たとえば、人間たちのように。
それなりにアロンは人間の歴史を知っている。戦争があることも、殺し合いがあることも知っている。
それでも、変化に富み発展し日々流動していくあの世界は輝かしいと思うのだ。
「……もし俺が人間だったら」
呟いて夢想してみる。自分が人間だったら、どうなんだろう。
あの世界で、朝と夜と季節の移り変わりを感じて、自分の成長を感じて、老化を感じて、そして。
……そこから先は、よくわからない。
魔に属するものは人間を食料程度にしか見ない。見ないというより、そういう態度を示すことがプライドであり、ステイタスなのだ。それなのに、魔界にいる魔物の大半が、人間に依存しなくては存在できないのは、どういうことなんだろう?
「……ま、んなこと考えても仕方ないか」
一人ごちて、回廊を歩きだす。
明日からしばらくは人間界だ。
向こうで過ごせる期間は決まっている。どんなに長くともせいぜい一年だ。
それを過ぎると、外見上に全く変化のないアロン達は、周囲に違和感を生じさせてしまう。
特にジョシュアは人間からすればまだまだ成長期の外見なのだから、注意しなくてはならない。
限りある時間、という制約は、アロンにとっては珍しい。
向こうで何が起きるかわからないが、期限があるのならその期限内を精一杯楽しみたいし、そのためには時間を有効に使わなくてはいけない。
時間を無駄にしないために頭を悩ませるということ自体が初めてで、アロンとしても、どう行動していいか、今一つピンと来なかった。
だがそういう悩みも、今までの停滞した日常を思えば、楽しい種類に入るのだろう。
現に今も、アロンの胸は明日からの生活への期待に高鳴っている。
自室の扉を開ける。そこには普段使用しているものが既にある程度荷造りされていて、アロンが手ずからしなくてはならないことは少ない。あとは遊興品を自分で選ぶくらいのものだ。
そしてふと、人間界で出会うべき少女について思った。
別荘の管理人という彼女は、どんな子だろう?
海で遊ぶのは好きだろうか。町に買い物に行くのは、夕暮れ時を散歩するのは。
こちらではできない遊びがたくさんありすぎて、一番最初に何をしたらいいのか迷ってしまう。
持っていくおもちゃを選べないジョシュアのことを笑えない。
笑えないがしかし、アロンは明日の旅立ちを楽しく迎えたいと思うのだ。
────END
|
|
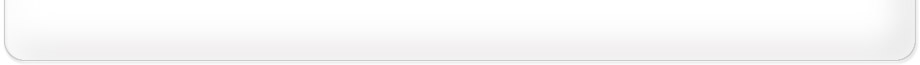 |