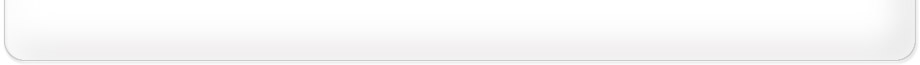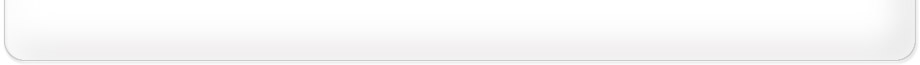|
彼の名前は知っている。
ミハイル=ヴァレンテ。
怜悧な眼差しに凍りつくような美貌、気高く由緒正しい血統、誰にも心を許さない孤高の存在。
彼に近づきたくて、一目でも見たくて、少女はその手段を必死に探してきた。ヴァレンテ家の一族の信奉者は多く、自分だけを見つめてもらうことは難しい。さらに言えば、少女はシルキーと呼ばれる儚い精霊であり、家事をするという変わった特徴がある以外、特に目立った能力もない存在だ。これで、彼に目をかけてもらいたいと思う方が間違っている。
けれど、美しいと思ってしまったのだ。
本当にたまたま、彼が町に面した窓際に立った、その姿を。
|
 |
|
彼を想うのは幸福だった。
人間界に悪戯をしに行くこともやめ、ただ、ヴァレンテの家の動向にだけ意識を向けた。
考えることを放棄し、ただ、彼の人の姿を見たいと願うことは、楽しかった。
だから、少女は迷わない。
今日も彼女は、ヴァレンテ家の居城を見つめ続けている。
* * *
|
|
一晩中歩くことは苦痛ではない。
だが、目的のものが見つからないというのは不愉快だった。
町の片隅で立ち止まりミハイルは息を吐いた。足を止めると周囲の喧噪がより一層大きく耳に響いてくる。静寂を好むミハイルには拷問のようだ。
兄であるファウストはこの喧噪のどこが良いのか、たびたび城を抜け出しては町に来ているらしい。今夜もこの町の中のどこかにはいるはずだが、さて、どこにいるのか。気配を頼りにこの一角まで来たものの、ここまで来てその気配が途絶えてしまった。どうしてこう厄介事を起こすのか、と、ミハイルはわずかに眉を寄せた。
普段であれば、ファウストが遊びに出ようと知ったことではない。どうせ長くても一か月程度で戻ってくるのだ。敢えて探したりはしない。だが、今日はそういうわけにはいかなかった。
ファウストを長兄とするヴァレンテ家の四兄弟は、明日には人間界に旅立たなくてはならない。放っておけばいつ帰ってくるかわからないファウストを、ただ待っていることはできないのだ。
石畳の上を歩きながら、ミハイルは空を見上げた。空には鈍い色の月がある。夜も昼もなく輝く淡い光。この世界には、人間界のように太陽はない。けれど明日、再びあの強い光の下に出なくてはならない。
あの、耐えがたい記憶と苦痛を具現したかのような、浄化の光の下に。
「……太陽、か」
ミハイルの知っている太陽の光は、くすんだ町の片隅の、森とも林ともつかない未開拓地を照らすそれだ。枯れて焦げたような木々に、頼りなくしかし濃密に天を覆う緑。その隙間から滲む灰色の陽光。そこで出会った、彼女。
嘔吐感に似た痛みを無表情に飲み下して、ミハイルはまた歩を進める。追憶から浮上する。ミハイルの内側に張り付いて腐り落ちそうな悲哀は、もうミハイルを構成する一部になっている。自分が命を終えるときに、この痛みもようやく終焉を迎えるのだろう。
ファウストの気配はいまだつかめず、ミハイルの目の前の闇の中を無数の化け物たちが通り過ぎていく。彼らは文字通り化け物だが、ある程度は社会性のある存在であり、同時に、人間の形に比較的近いものが多い。理性のないものはこの世界でも集団へは属せないし、少なくとも、このような町には来ることがないよう、領主であるミハイルの父が防壁を張っている。それもまた、ヴァレンテの一族の仕事だ。
その闇の向こうに、少女の姿をした何かが身を潜め、こちらを覗きこんでいるとミハイルは知覚した。儚い存在で、ヴァンパイアではないことはすぐにわかった。ただじっとこちらを見つめている。ミハイルは足を止め、その姿を直視する。
ヴァンパイアの視線には誘引能力がある。隠れていた少女が、ふらりと夢を見ているようにミハイルに向かって数歩歩きだした。闇が晴れ、その姿が明らかになる。緑に近い影が印象的な線の細い少女だ。これは、シルキーだろう、とミハイルは思う。他愛もない悪戯をする弱い魔物だ。
「シルキーが私に何の用だ」
ミハイルの声に、少女がびくんと体を震わせた。やはり、弱い。ただ声だけで、鞭打たれたような反応を返してくる。
「あ、あの、私」
細い声がミハイルの耳に届く。
「貴方の、ヴァレンテ家の方の、信奉者です」
震える声の裏に、抑えがたい興奮と歓喜が滲んでいる。それをミハイルは、鬱陶しいと思った。
「こ、今夜、こんなところにいらっしゃるとは、
夢にも思いませんでした!
お会いできて光栄です……!」
頼りない声は、彼女を思い出させた。
広がったスカートに長い髪も、共通しているというだけで似てはいないのに、腹がたつほど心の琴線に触れてくる。
ざりざりと、爪を立てられる。
「あの、どうか、私に、いえ、私を……」
私をどうしろというのか
その願いが何なのか。
聞くことをせず、ミハイルは彼女を引き寄せた。それはとても容易いことだ。ただ、眼差しにより強く意志を乗せればいい。それだけで、獲物は首を差し出してくる。
「あ……!?」
シルキーの少女の脚が、踊るように数歩歩いた。本人の意志と関係のない動きに、輝いていた瞳が僅か、怯えを見せる。
「くだらない」
手を伸ばす。腕をつかむ。引き寄せて、驚きと恐怖に色を変えた彼女の顔を見ることもせず、ミハイルは少女の首筋にその牙を突き立てた。
「あ───────ッ……!!」
シルキーは人間ではないから、人と同じような血液は出ない。ただ、血液に似たものはある。ミハイルの舌に伝わるその味は人間のものほど芳醇ではないが、生命力を奪うという意味では人間に対する吸血と大差ない。
いや、命そのものをもぎ取るという意味では、こちらの方がより残酷だった。
「あ、あ、あ、い、あああ……」
必死に抵抗しようとした少女の悲鳴がどんどん細くなっていく。容赦なく突き立てた牙はシルキーの弱い表皮に傷をつけ、浸食を許している。今この少女は、全身を溶かされるような苦痛を味わっているはずだった。
「あ……や、たすけ……」
理解しろ。────ミハイルは思う。
触れてはならない存在があると。
癒すことのできない傷があると。
遠い星のように憧れていたいのなら、決して近寄ってはならない。
それは眩く輝くものではなく、一つの生命もその身に宿さない、冷たい無機物の塊なのだから。
永遠の虚空に漂うものに何の守りもなく手を伸ばせば、命は無いのだ。
「……あ……ァ」
もう声も出ないのか、細い少女の手足ががくがくと震えて、目障りだった。もう消滅の寸前だ。
ミハイルはこのまま殺そうかと一瞬考える。が、それもくだらないと、少女の体を引き剥がす。
石畳に崩れた少女の体はもはや輪郭を保つのみだ。シルキーは声もなく、絶望的な恐怖を瞳に宿して、ミハイルを見上げている。
ほんの少し前の、浮かれていた様子とは大違いだな、と、ミハイルは冷たく思う。
「迂闊にヴァンパイアに近づくとは、愚かな娘だ」
周囲の闇が蠢き始めた。死に瀕した少女の気配に、細かな魔物が集まり始めている。
放っておけば消え去ることはないだろう。そう、一年ほど身を潜めていれば回復する。その程度のものだ。
「二度と私の前に姿を見せるな」
言い放ち、ミハイルは少女に背を向けた。
振り返ることはしなかった。
* * *
「兄さん、戻ってきたのか!」
城の広間を抜けたところで、アロンがミハイルに気づいて声を上げた。ミハイルに向かって駆けてくる。
「ファウストは?」
「兄貴なら、今は部屋だ」
しばらく前に町で捕獲したファウストは、今は部屋に押し込められている。おそらく、執事に絞られていることだろう。長兄の自覚、後継者の責任、そんなものを聞かされているに違いない。
「そうか、よかった。けどよく見つかったなぁ。
探しに出たの、昨日の晩だろ?」
「一度見失った。少し探すのに手間取った」
「だんだん城を抜け出すのがうまくなってくよな、ファウスト兄貴」
アロンは苦笑いを浮かべ、ミハイルと並んで歩き出す。が、何かに気づいて眉を潜めた。
「……嫌な臭いがする。血に似てるけど、血じゃない」
その言葉には責める響きが混じっているが、ミハイルは無言で返した。アロンは眉を潜めながら、どこか哀しげな顔をしている。能天気に見えて動じることが少ないファウストと違い、アロンははっきり喜怒哀楽を表に出す。それが悪いとは言わないが、時折、扱いに困るのも事実だった。
「……あんまり酷いことをするなよ。可哀そうだ」
誰が可哀そうかは言わず、アロンは息を吐く。ミハイルは何かを言おうとしたが、特に言うべき言葉が見つからないのでやめた。ただ黙って二人、自分の部屋へと歩いて行く。
「……ジョシュアはどうしてる?」
「ん? ああ、おもちゃを選んでるよ。あんまりたくさん持っていかないように言ったんだけど、凄いことになりそうだ」
肩をすくめて言って、アロンは廊下の突き当たりで足を止めた。ミハイルに片手をあげて道をそれる。
「じゃあな、兄さん。明日は午前中に父さんに挨拶だから、寝過ごすなよ!」
「……言われるまでもない」
アロンを見送り、ミハイルは自分の部屋の扉を開く。
何もない暗い部屋だ。群青色の床の上を歩いて、ソファに身を埋めた。
「人間界、か……」
眩暈がする。嘔吐感がこみ上げる。行きたくない。だが、行くことが務めだ。逃げることも許されてはいるが、逃げてはならない。目を逸らしても逸らさなくても現実は何も変わらないのなら、するべきことをした方がいい。
人間界の太陽を思い出す。
その灼熱は浄化の力にあふれているが、残念ながら、ミハイルのような純血のヴァンパイアは、そんなものでは滅びない。
いっそ焼け落ちるほどの炎であればよいものを、その願いは叶わない。
ほんの刹那、牙を突き立てたシルキーの少女が頭をよぎる。
少女に見える女はミハイルにとって絶望の象徴だ。拭えない痛みの形だ。だが、人間界で出会わなければならないのも、また、少女なのだ。
「……殺さないようにしなくては」
目障りだと消去してしまわないように。
または、壊す前に保存してしまおうなどと、思わないように。
ミハイルは瞳を閉じる。
窓の外の月が白く輝いていた。
────END
|
|