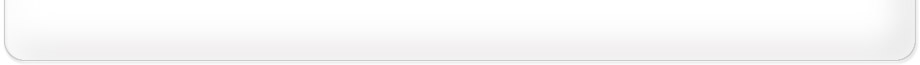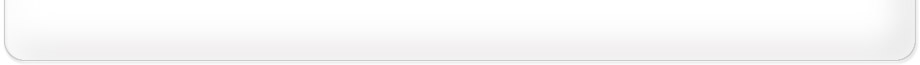|
暗く蒼い月光が石の部屋を照らしだしていた。
蒼光はたゆたい、水槽の中で目覚めたのかと、ほんの一瞬錯覚する。
ここがどこなのか、今がいつなのか、そういう瑣末事はわからなかったが、窓際に佇む背の高い女が美しかったので、とりあえず物事を考えずに彼女を見つめていることにする。
ファウストの視線を受けても臆することなく薄い笑みを浮かべている姿に、いいな、と思った。
表情や顔立ちははっきりと際立っているのに、今にも消え入りそうな透明感のある、美しい女だ。
ローレライか、とも思うが、断定はできない。
彼女の手にはティーカップがあった。女はふいに歩き出し、テーブルの上の水差しからグラスに濃い色の液体を注いだ。良く冷えているらしい。グラスの軋む音が、聴力に優れたファウストの耳に届く。
|
 |
|
「どうぞ」
ファウストの鼻先に、そのグラスが差し出された。
「……悪い」
身を起こしながら、水滴の付き始めているグラスを受け取った。硬い感触のベッドだった。ベッドなのか、ソファなのか判然としない。
|
|
それ以前に石室同然のこの部屋は、本当に部屋なのかどうかもわからなかった。石がむき出しの壁があり、床があり、かなり高い位置に岩を切り抜いたような形の大きな窓がある。窓かもしれないが、出入り口かもしれない。もし、女が重力にとらわれないタイプの存在ならば、の話だが。
色の割に味の薄い飲み物を飲みながら、状況を整理する。ここはファウストの居城、ヴァレンテ家の城ではない。けれど領地内のどこかだろう。そう言えば自分は昨夜遅くにこっそりと城を出た気がする。
そうしていつも通り町に出て、おそらく、どこかで呑んで、適当に女をひっかけて。
その女が、目の前にいる彼女なのだ。
「悪い、昨夜のこと、あんまり記憶にないんだが」
単刀直入にそう切り出すと、女は驚いた様子もなく、わずかに首を傾ける。
「俺は何か無礼な真似はしなかったかな。君が不愉快に思うようなことを」
女は薄く笑い、答えることはしなかった。肯定でも否定でもないが、とりあえず嫌悪されてはいないのだろう。ファウストは肩をすくめ、立ち上がった。空になったグラスを無機的なテーブルの上に置く。カツン、と硬質の音が響いた。
「ゆうべ、初めて会ったのよ。
私は貴方の名前も、どこの誰かも知らない」
謡う様に話すかと思ったが、むしろそっけなく女は言った。ファウストは女を見つめたが、彼女は自分を見てはいなかった。
「俺もだ。君の名を知らない。
今から聞いてもいいかい?」
「教えない。知らないままでいたほうが楽しいわ。全部知ってしまったら終わりだもの」
「……そうだな。恋に落ちるのもあっという間だが、飽きるのはもっと早い。君の言う通り、一度に多くを知らないほうが楽しい」
女の態度は良くも悪くもなく、ただ、淡々としていた。冷淡とも言えるかもしれないが、ファウストはそれが心地よかった。幼い女は可愛いが、澄んだ水のような女も、美しいと思う。
窓から漏れる光から察するに、外は朝なのだろう。朝と言っても、月の光が強くなる程度の変化しかこの世界には起きないから、大した意味はないのだが、時間経過の目安にはなる。
「よくこの町には来るみたいね」
女は言って、その言葉にファウストは苦笑する。
「ああ、そんな話をしたかな。暇なものでね」
「貴方を以前も見かけたことがあったの。
誰かを探しているみたいだった」
「別に誰も探してた覚えはないが、物欲しそうだったかな」
「そうね、退屈そうだった」
退屈なのは事実だった。城にいるのも、町をうろつくのも飽きてきて、いい加減することがない。
「一生が永すぎる。そう思うのは俺だけかな」
「……どうかしら。私はまだ生き飽きてはいないけれど」
「俺もまだ消えたいわけじゃない。ただ、退屈なんだ」
しなくてはいけないことが、あるような、ないような。
課せられたものはある。ヴァレンテ家長兄として、家を継がなくてはならない。それは重大な責務だが、それだけだ。
家を継ぐ、それはただ存在せよと言われるのと同じこと。継いだ後に何をするか、どう生きていくかということについては関係がない。
それに、存在するために生きろというのは重く、鬱陶しい。今以上に城に拘束されるなど、耐えがたいように思える。ファウストがもし退屈を毒とするなら、とっくに死んでいることだろう。
積極的に何かがしたいわけではない。
ただ、毎日がつまらない。
────しかしその退屈な日々が、少しばかり変わろうとしていた。
「しばらくこの町へは来ないと思う」
そう言って、ファウストは女に近づく。
髪は白銀を帯びているように見えていたが、傍で見ると深い湖のように蒼かった。瞳の色も同じく、美しい色をしている。
「人間界へ行かないといけないんだ。どのくらいの期間になるかわからないが、再会を祈っててくれ」
女は目を幽かに眇め、立ち止まったファウストに一歩近づいた。
「いいえ、もう来ては駄目。
深窓の貴公子はお城から出ないほうがいいのよ、ヴァレンテ家の王子様」
女の言葉に、ファウストは苦笑する。
「なんだ、バレてたのか」
「隠しても無駄よ。貴方がヴァンパイアだということは、一目でわかったわ」
女は笑い、そっと指を持ち上げた。
細く血の気のない白い指で、ファウストの唇に触れる。
「貴方にプレゼントをあげる」
驚く暇もなく、彼女の指から閃光のようなものがファウストの脳裏に突き抜けた。
刹那、思い浮かぶ幻想。
白い家。
美しい丘。
そこに住む少女
風に揺れるカーテン。
溢れる光。
それから────青い炎。
眩暈は一瞬で、ファウストはすぐに視界を取り戻した。
目の前には一秒前と変わらず女がいて、ファウストの唇に触れている。彼女は笑みを浮かべたまま、ゆっくりと指を引いた。
「君はローレライかと思ったんだが、ラナン・シーだったのか」
息を吐きながらファウストは呟いた。
ラナン・シー。
水辺を好む美しい魔女。自分に恋をした男の命を糧とする代わりに、神託の如き導きを与える存在。
与えられた閃きに、指先を額に当てて眉を寄せていたファウストを見て、彼女は一歩身を引いた。
「いらないお世話だったかしら」
「いや、ありがたい。何かが起きそうだということはわかった」
女はファウストから離れながら、壁際に歩いて行く。その後ろ姿を眺めていたファウストは、立ち去る時間なのだと気がついた。
「その幻想が導きになるかどうかは貴方次第。
美しい夢が見られるように祈っているわ」
それを別れの言葉とし、ファウストは軽く跳躍した。一瞬で数メートルの高さをゼロにして、窓のへりに立つ。
「次に会うことがあれば、名前を聞くよ」
見下ろした石の部屋で、女は肩越しに振り向いて、ほんのわずか、微笑みを浮かべた。
* * *
「今までどこにいた」
感情のない顔に感情のない声で、ファウストの弟はそう言った。限りなく無表情だが、実はこれで激怒していることを、ファウストは経験から知っている。
「早く城に戻れと言われていたはずだが」
「そうだったかな。……いつから探してた? ミハイル」
「昨晩だ」
ああ、昨晩ね、昨晩。と呟いて、ファウストは視線を逸らす。まさかあの石室を後にしてすぐ弟に捕獲されるとは思っていなかった。しかも、よりにもよってミハイルに。
「いやしかし、お前がこっちまで出てくるとは珍しいな。町は嫌いなんじゃなかったのか」
「嫌いだが、探す対象が町に行ったのだから仕方ない。したがって今、非常に不愉快だ」
「好き嫌いしてると大きくなれないぞ」
「それはどこの世界の常識だ?」
「人間界ではそういう都市伝説があるらしいぜ」
嘯いて、ファウストはミハイルから視線を逸らし、始終何かがうごめく気配のする薄い闇の向こうを眺めた。こちらの町は、どこに何があってどういうものが住んでいて、というのが一定しない。ただ全体の変化は少ない。町というよりは、わだかまっている者達と言ったほうが正しいのかもしれなかった。
ファウストはこの町が嫌いではないが、ミハイルはひどく嫌っていた。曰く、雑多なものが好きではないという。────だが。
「お前、俺を探しながら何をしていた?」
陶器の人形のようなミハイルにファウストは問いかけた。ミハイルは答えない。ファウストの嗅覚は、ミハイルから漂うかすかな血臭をとらえている。血とは限らないが、血液に近い、何かの臭いだ。
「軽い食事だ」
淡々とそう返し、ミハイルは歩き出す。それ以上の回答は期待できそうにないので、ファウストも並んで歩き始めた。この弟にはしつこく聞いても時間の無駄だ。答えないものは何をどうしても答えないのだから。
旅立ちのために自分を迎えにきたという弟に、ファウストはふと問いかけた。
「ミハイル。お前、人間界についてどう思う?」
ミハイルからの返事はないが、ほんのわずか、ミハイルの瞳に昏い色が走り抜けた。
絶望の色。癒えない傷の記憶。
ああ、やはりまだ、と、心の中でファウストは呟く。人間界は鬼門だ。特に、この弟にとっては。
場合によってはミハイルだけでも先にこちらに戻すべきかもしれない、と心の中に留めておく。
けれど────重い気分を抱えると同時に、ファウストは思う。
先刻ラナン・シーの女に与えられた幻想の中に、忌まわしいものはなかったような気がする。
あったのは、清浄な輝きであり、魔に属する自分ですら魅了する、優しいあたたかさだった。
もっとも幻想は幻想であり、それ以上では決してないのだと、わかってもいるのだが。
ファウストは遠い居城に視線を向けた。明日にはあの城を出て、人間界へ旅立つ。そこに何が待ち受けているか、ファウストにはまだ見えない。
ただ少しでもこの退屈が紛らわされることを願って、歩き続けた。
────END
|
|